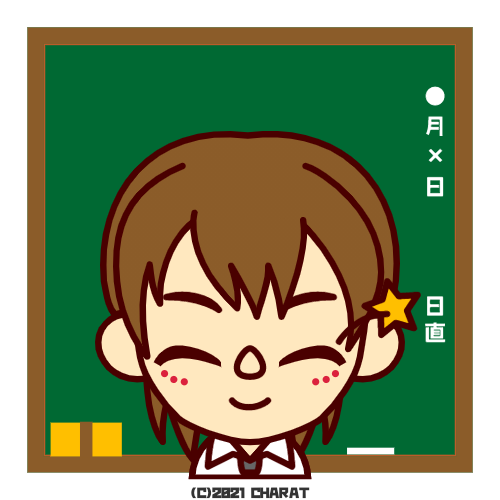今回の基礎看護技術は、包帯法について述べていこうと思います!
今どき看護師さんって、包帯を巻いたりするの?
ネット包帯とかが主流な気もするんですけど・・・
そうですね。
以前に比べて、包帯を巻く機会も減ったのかもです。
でも、完全になくなったわけじゃないです!
ケガをしてガーゼを固定するのに包帯を巻く
→ 創傷被覆のドレッシング材が出てきたので、貼付するだけになりましたね。
下肢に弾性包帯を巻く
→ これはしている施設もありますが、弾性ストッキングがほとんどですよね。
静脈留置針の保護、ガーゼ使用時の保護
→ ネット包帯で巻くことが多くなりました。
ほかにもいろいろと包帯がしていた役割を、ほかの便利で効果があるものに変わっていったことはたくさんあると思います。
(なにかほかにもあれば教えてください!)
しかし・・・
急にきます!
これは包帯の方が固定しやすいのではないか!って時が
静脈留置針の自己抜去予防のとき、関節の固定、シーネの固定
などなど
看護技術として基本的なことだけでも覚えておくことは、大事ですよね!
ということで、今回は包帯法の基本について解説していきます。
- 巻き始めと巻き終わりの「環行帯」
- 一般的な巻き方「らせん帯」
この2つだけ!できるようになると看護の幅が格段に上がります。
包帯の基本から2つの巻き方について解説していきますね。
本記事の参考図書です。
僕も実際に授業資料の作成に役立てることができていますので、おすすめですよ。
包帯法について
包帯とは、創傷や骨折などの治療のために用いられる衛生材料や器具のことです。
包帯法は、目的に応じて包帯の素材・方法を選び用いる技術のことをいいます。
包帯は、紀元前2500年ごろのメソポタミアで行われていたリネンを用いた被覆法が最古と言われています
包帯法の目的
次のような目的があります。
| 被覆 | 創傷部を覆い、科学的・物理的刺激などの外的な刺激から保護をします。 |
| 支持 | 創部に用いた薬剤、張り薬などのずれや剥がれるのを防止します。 |
| 固定 | 運動の制限、痛みの緩和を目的に骨折や捻挫、脱臼などの際に骨と関節を固定します。 |
| 圧迫 | 出血部位の止血のための圧迫、下肢に巻いて静脈還流の促進などです。 |
| 牽引 | 骨折部の牽引に使います。 |
| 保温 | 部位の保温などがあります。 |
| 安楽 | 疼痛、倦怠感を緩和、創傷部を覆い見えなくすることで精神的な苦痛の緩和などです。 |
包帯の種類
包帯にはいくつかの種類がありますので、用途に応じて選んでいきましょう。
三角巾やギプス、ネット包帯などもありますが、複雑になってしまうので、今回は巻軸帯のみにしますね。

(かんじくたい)
| 綿包帯 | 木綿布を長く裂いたものになります。ちょっと堅くて伸縮性はありません。 |
| 伸縮包帯 | 色々な素材でできています。部位の形状にフィットしやすくズレが生じにくいです。一般的に出回っている包帯は伸縮包帯です。 |
| 弾性包帯 | ゴム素材が含まれた厚めの包帯で、強い伸縮性があり、圧迫や固定に向いています。静脈還流を促すために下肢に巻いたりします。 |
| 粘着包帯 | 粘着性のあるテープ型。テーピングに使用したりしています。 |
包帯法の実際
包帯法の原則
包帯は、目的や部位に適したものを選びましょう。
部位に応じた幅や種類がいいですね。
一般的には、上下肢は4~6号、指は8号、肩は4~5号と言われています。(号数は包帯によって違うこともあるので、しっかりと患者さんに合わせた幅を選んでくださいね)
感染予防を意識しましょう。
清潔な物品を使用しましょう。
使いまわしなどは避けてくださいね。
汚染した場合はすぐに交感してください。
皮膚の2面が接しないようにします。
肘や指、脇など皮膚同士をくっつけてまとめて巻くようにしないようにしましょう。
2面が接して固定をすると、摩擦や圧迫による損傷や蒸れてしまい不潔になってしまいます。
循環障害を防止しましょう。
一定の圧力で、患者さんに向かって左から右へ、転がすように巻きます。
末梢から中枢に向かって巻きます。
観察できるように抹消は露出しておきましょう。
ラプラスの法則
同じ圧力を加えた場合、太さが大きくなるほどかかる圧力は小さくなります。
この法則から、抹消側が細く、中枢側が太い形状の部位では、抹消から中枢に向かって一定の圧力で巻くことで、静脈還流を促す圧差ができます。
転がしながら皮膚に沿わすようにしましょう。
しっかり巻こうと思って、引っ張ったり、きつく伸ばしながら巻いたりすると、伸縮包帯の場合は、戻ろうとする力が加わって逆にすぐに緩んできてしまいます。
皮膚に密着させて皮膚に沿わせながらコロコロ、コロコロ!
包帯の面と皮膚の面を密着させることで、摩擦力が最大限となり、緩みにくい巻き方ができます。
緩まないようにって思ってグイグイやると、余計に緩みやすくなったり、圧迫が強くなってしまったりするので、気をつけましょう!
ベッドメーキングでも同じです。マットレスとシーツをしっかり沿わせて、密着させると崩れにくいベッドができるようになりますよ!
包帯の巻き方
包帯法の種類(巻き方)
| 環行帯 | 同じ部位を重ねて環状に巻く方法です。巻き始めと巻き終わりに行います。 | 巻き始め、巻き終わり |
| らせん帯 | 先に巻いた包帯の上を1/2~1/3程度重ねてらせん状に巻いていきます。 | 長さがある部位に用います |
| 蛇行帯 | 包帯を重ねずに一定の間隔をあけてらせん状に巻いていきます。 | 広い範囲のガーゼやシーネを固定する際など |
| 折転帯 | 包帯を重ねて幕が、人巻きごとに折り返して巻いていきます。(最近の包帯は伸縮包帯がほとんどですので、あまり使う機会がないかも…) | 太さが大きく変化する部位 |
| 亀甲帯 | 8の字を描くように屈側で交差させて巻きます。 | 肘関節、膝関節など |
| 麦穂帯 | 8の字を描くように伸側え交差させて巻きます。 | 手関節、足関節など |
今回は、環行帯、らせん帯についてやっていきましょう。
頻回に包帯を使用する診療科(整形等)以外は、らせん帯をマスターしていたら行けるとおもいます!
環行帯
環行帯(かんこうたい)は、同じ部位に重ねて巻きます。
どの包帯の巻き方でも、始めと終わりは環行帯です!
環行帯の始めは少し斜めにして角を出します。








これで環行帯の出来上がりです。
環行帯について、よかったら動画も参考にしてくださいね。
らせん帯
先に巻いた包帯の幅の1/2~1/3を重ねながら巻きます。
巻き始めは必ず環行帯です。

らせん状に巻いていきましょう。




これでらせん帯の出来上がりです。
らせん帯について、よかったら動画も参考にしてくださいね!
おわりに
どうでしょうか。
包帯の基礎的な技術としてのらせん帯は、ふとした時に活躍してくれます。
ほかにも麦穂帯や亀甲帯などは、今回は割愛させていただきました。
これらの巻き方は、学校やご家庭などの病棟以外の場所で使用することはあるかもしれませんね。
ぜひ、基本の環行帯、らせん帯だけでも正しく巻けるようになってもらえたらなと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。